神社の経営・収入源はなんだろう~?と思ったのが今回のキッカケです。
神代期(天地開闢~神武天皇即位まで)に創建された、「伊弉諾神宮」や「大神神社」は最古の神社と言われています。
その中で、神社の紹介にでてくる「官幣大社」「一宮」「二十二社」などは社格といい、神社の格式にあたります。
社格の歴史(流れ)は
①上古社格制度:~法整備される前
②古代社格制度:飛鳥時代から
③中世社格制度:平安時代中期/後期から
④近代社格制度:明治時代初期から
と分類されています。
しかし、現代は
太平洋戦争後、GHQの神道指令によって社格制度自体は廃止存在しません、ただ位置づけ・ランキングとしての格のように扱われています。
現在は、神道本庁が神社を包括する宗教法人として、神社も宗教団体としての位置にある。
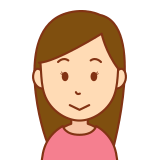
天地開闢(てんちかいびゃく)
天と地が初めてできた、世界のはじまりの意
上古社格制度
古事記や日本書紀が編纂される前の制度
●「天津社」:天津神を祀る神社
●「国津社」:国津神を祀る神社
古代社格制度
701年 飛鳥時代 42代文武天皇 「大宝律令」完成し規定されたとされる。
927年 平安時代 60代醍醐天皇 「延喜式神名帳」全国の神社一覧が記されている。
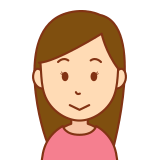
大宝律令は、681年
40代天武天皇の命で始まります
●「式内社」: 延喜式神名帳に記載された神社で2861社ある。
・官幣社 : 新祇官から幣帛を受ける神社
官幣大社 198社 304座
官幣小社 375社 433座
・国弊社 : 国司から幣帛を受ける神社
国幣大社 155社 188座
国幣小社 2133社 2207座
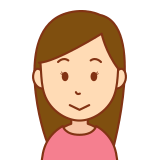
幣帛(へいはく)とは
神様へのお供え物のこと
●「式外社」:延喜式神名帳に記載されていない神社(石清水八幡宮、北野神社など)
・国史見在社:六国史に記載がある神社 391社(座)
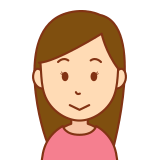
六国史、古い順に
①日本書紀 ②続日本紀 ③日本後紀 ④続日本後紀 ⑤日本文徳天皇実録 ⑥日本三代実録
中世社格制度
成立時期は、不明。
798年 国弊社の成立
遠隔地の神社は、交通の不便を理由に神祇官から幣帛受け取りをしないことから始まります。
国司から幣帛を受け取る形になります。
その後国司の神拝は、地方の有力神社から行われるようになる。
8世紀 律令国家体制 ~ 10世紀 王朝国家体制
中央集権政治の指示伝達/統治は、地方行政の国がささえでした(実際に仕事をする人)。
しかし地方行政に限界が生じ地方政治委任/委託に移り変わります。
つまり個別人身支配原則から土地課税原則への移り変わりです。
新たな社格制度誕生
●「二十二社」:国家の大事、天変地異など、臨時に朝廷から幣帛を受ける神社。
格式の高い順に、「上七社」「中七社」「下八社」に分けられており、下記一覧です。
選考は天皇・朝廷・藤原家ゆかりの神社が多く、鎮守社・鎮守神として都中心の場所が多い。
*この当時藤原家の摂関政治による権力の威光が強い。
・上七社
伊勢神宮(三重県伊勢市宇治館町1)
石清水八幡宮(京都府八幡市八幡高坊30)
上賀茂神社(京都市北区上賀茂本山339)
下鴨神社(京都市左京区下鴨泉川町59)
松尾大社(京都市西京区嵐山宮町3)
平野神社(京都市北区平野宮本町1)
伏見稲荷神社(京都市伏見区深草藪ノ内町68)
春日大社(奈良県奈良市春日野町160)
・中七社
大原野神社(京都市西京区大原野南春日町1152)
大神神社(奈良県桜井市三輪1422)
石上神宮(奈良県天理市布留町384)
大和神社(奈良県天理市新泉町星山306)
廣瀬大社(奈良県北葛城郡河合町大字川合99)
龍田大社(奈良県生駒郡三郷町立野南1-29-1)
住吉大社(大阪市住吉区住吉2-9-89)
・下八社
日吉大社(滋賀県大津市坂本5-1-1)
梅宮大社(京都市右京区梅津フケノ川町30)
吉田神社(京都市左京区吉田神楽岡町30)
廣田神社(兵庫県西宮市大社町7-7)
八坂神社(京都市東山区祇園町北側625)
北野天満宮(京都市上京区馬喰町)
丹生川上神社中社(奈良県吉野郡東吉野村大字小968)
丹生川上神社上社(奈良県吉野郡川上村大字迫167)
丹生川上神社下社(奈良県吉野郡下市町長谷1-1)
貴船神社(京都市左京区鞍馬貴船町180)
●「一宮」:地域(国)から幣帛を受ける一番社格が高いとされる神社。
地域(国)によっては「二宮」「三宮」とあり、国司が神拝する順番とされるのが通説です。
例:尾張国 一宮 真清田神社(愛知県一宮市)
二宮 大懸神社(愛知県犬山市)
三宮 熱田神宮(愛知県名古屋市)
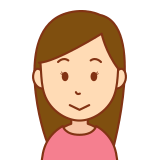
江戸時代までは令制国であり
国は「68」ヶ国ありました
●「惣社」:総社ともいう。
地域(国)にある神社のご祭神を1ヶ所に勧請して祀った神社。
国司の巡拝省略可が目的です。
●「国司奉幣社」:各国の国内神名帳に記載のある神社。
近代社格制度
明治維新にはいり、神仏分離のもと再編成されることになります。
伊勢神宮は全神社の上にあり、社格のない存在とされます。
●「官社」:律令に倣って、官弊社と国幣社にわかれ、それぞれ大社/中社/小社の格がある。
官国幣社ともいう。
官幣大社 62社
官幣中社 26社
官幣小社 5社
国幣大社 6社
国幣中社 47社
国幣小社 44社
●「別格官弊社」:国家の功労者を祀られた神社。
28社
例:豊臣秀吉の豊国神社
前田利家の尾山神社
靖国神社など
●「諸社」:府県社、郷社、村社に分類される。民社ともいう。
府県社:道府県から幣帛を受ける神社 1148社
郷 社:府県または市から幣帛を受ける神社 3633社
村 社:村から幣帛を受ける神社 44934社
●「無社格」:社格を有しない神社。
当時の神社半数以上が無社格 59997社
●「神饌幣帛料供進社」
郷社/村社を対象に、明治から終戦に至るまで勅令に基づき県令をもって県知事から
祈年祭、新嘗祭、例祭に神饌幣帛料を供進された神社。
社格とは別の制度
●「勅祭社」:祭礼の際に、天皇から勅使が遣わされる神社。16社
1868年明治天皇が氷川神社の祭事を勅祭したのがはじまり。
上賀茂神社(京都市北区上賀茂本山339)
下鴨神社(京都市左京区下鴨泉川町59)
石清水八幡宮(京都府八幡市八幡高坊30)
春日大社(奈良県奈良市春日野町160)
氷川神社(埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-407)
熱田神宮(名古屋市熱田区神宮1-1-1)
橿原神宮(奈良県橿原市久米町934)
出雲大社(島根県出雲市大社町杵築東195)
鹿島神宮(茨城県城県鹿嶋市宮中2306-1)
香取神宮(千葉県香取市香取1697)
近江神宮(滋賀県大津市神宮町1-1)
平安神宮(京都市左京区岡崎西天王町97)
明治神宮(東京都渋谷区代々木神園町1-1)
靖国神社(東京都千代田区九段北3-1-1)
宇佐神宮(大分県宇佐市大字南宇佐2859)
香椎宮(福岡市東区香椎4-16-1)
●「准勅祭社」:1868年東京と付近12社を准勅祭社としたが、1870年廃止。
1975年東京十社として現在にいたる。
根津神社(東京都文京区根津1-28-9)
芝大神宮(東京都港区芝大門1-12-7)
神田神社(東京都千代田区外神田2-16-2)
日枝神社(東京都千代田区永田町2-10-5)
亀戸天神社(東京都江東区亀戸3-6-1)
白山神社(東京都文京区白山5-31-26)
品川神社(東京都品川区北品川3-7-15)
富岡八幡宮(東京都江東区富岡1-20-3)
王子神社(東京都北区王子本町1-1-12)
氷川神社(東京都港区赤坂6-10-12)
●「内務大臣指定護国神社」:1939年内部大臣が指定した護国神社。34社
太平洋戦争末期までに17社が指定を受け51社になった。
現代
1946年 1月13日 GHQは「神道指令」により神祇院を廃止
1946年 2月3日 宗教法人「神社本庁」設立
●「別表神社」
近代社格制度が廃止になり、すべての神社は対等の立場であるとされた(伊勢神宮は除く)。
しかし旧官国幣社や一部の規模の大きな神社については、神職の進退等に関して一般神社と同じ扱
いをすると不都合があることから、「役職員進退に関する規程」を設けることになります。
その対象となる神社が別表神社になる。
2006年の時点で別表神社は353社となっている。
最後に(神社存続へ)
以前、神社敷地内にマンション設立し、1・2階を社務所として活用するニュースをみました。
神社存続への対応手段です。
歴史ある神社でしたが、周囲はオフィスビルが多く、氏子の減少が要因の1つであり
そこへ地震による本殿を立て替えるための費用捻出が必要になったからだそうです。
神社の収入源は
・お賽銭
・神社グッズ(御守り、絵馬など)
・祈祷料(結婚式、七五三など)
・氏子からの奉納金、寄付金 などです
神社の支出は
・本殿など境内管理費
・神社グッズ作成費用
・神職関係者の人件費 などです。
以前の格式が高い神社であれば、運営費用は賄えるかもしれません。
人口減少や働き手の流出など、収入源の約4割を占めると言われる氏子費用の減少は、神社経営にとっては痛手です。
神社の数は約80,000社あり、コンビニの数は約57,000店(2021年)。
神社のほかに寺院を合わせると、神社寺院で約160,000あります。
商店街の活性化・温泉地の活性化など、人口減少にともなう過疎化の取り組みは、神社寺院におよびます。
旧社格や一宮など、現在社格は存在しませんがブランディングのためには仕方のないことかもしれません。
日本文化/伝統存続のために、いま私たちが出来ることを考えて行動することが大事だと思います。
まずは、お賽銭にも気を使ってみることにします。
そして、温泉地へ湯治?に行ってきます。
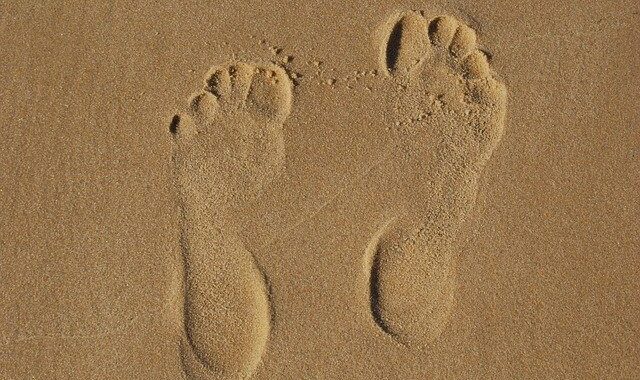



コメント