戦国武将人気ランキングでも常に上位、名古屋市中村区が誕生の地
農民から天下人になった豊臣秀吉ゆかりの「豊国神社」「常泉寺」に
熊本城など数多くのお城に携わった築城の名手加藤清正ゆかりの「妙行寺」を漫遊~
地下鉄東山線で名古屋駅から3駅「中村日赤」駅でおり、清正公通を西へ徒歩9分で到着します。
私のおすすめは、「中村日赤」駅の次「中村公園」駅から豊國参道を北へ徒歩9分で行くルートです。
地下鉄から地上にあがり、すぐ目に入るのが「中村の大鳥居」、創建当時は世界一高い鳥居でした。
京都の「平安神宮大鳥居」と同じぐらいの歴史を持ち、若干高い(1930年1月1日竣工式)そうです。
鳥居から豊国神社までは豊國参道と呼ばれ、毎年5月18日直前の日曜日には例祭(太閤祭)を行います。
沿道には屋台・縁日が並び、お神輿や盆踊りなど、2日間で数10万人の来場者でにぎわいをみせます。
豊国神社
【豊国神社】
鎮座地:名古屋市中村区中村町木下屋敷
ご祭神:豊臣秀吉
創 建:1883年
京都市の豊国神社
1598年8月18日に亡くなった豊臣秀吉の遺体は火葬されることなく、京都の伏見城に安置されてました。
遺言により阿弥陀ヶ峰に埋葬され、廟所を建立されたのが始まりです。
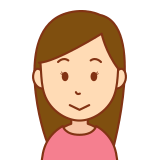
1615年徳川家康の命により、1度は廃絶させられます
名古屋市の豊国神社は、1883年太閤豊臣秀吉の生誕地荒廃を嘆いた当時の県令国定廉平や地元の有志らによって創建されました。
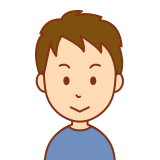
太閤とは、摂政や関白の職を退いて
子供が摂関の職についた人のこと
1883年の出来事と言えば
・7月 岩倉具視の国葬
・8月 伊藤博文がドイツ・オーストリア憲法調査から帰国、2年後1885年初代内閣総理大臣になる。
・10月 ヨーロッパの長距離夜行列車、オリエント急行開通
・11月 鹿鳴館が開館
まだ明治維新(1868年)から15年後の事です。
【中村公園】
豊国神社は中村公園内にあり、日本庭園を楽しみながら憩いの場として地元の方にも親しまれている場所です。
「初代中村勘三郎記念像」
・江戸時代初期の歌舞伎役者、初代中村勘三郎は1598年名古屋市中村区に生まれました。
2017年5月に彫刻家の津野充聡作の誕生記念像が建立し、新たな名所としてしています。
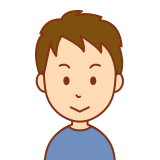
猿若勘三郎として知られる、初代中村勘三郎
同じ出身の豊臣秀吉の愛称は「サル」
関係性あるのかな~
「茶室」
・日本庭園をながめ、2軒の茶室。
桐蔭茶室、豊公領で風情ある茶会をもうけることができます。
「中村公園記念館」
・加藤清正没300年を記念して、愛知県が迎賓館として1968年に建てた。
明治時代に建築された公共木造建築物で、名古屋市では最古になる。
当時皇太子(大正天皇)が休憩所として使用したこたでも有名です。
お手植えの松も、現在では立派に育っています。
常泉寺
【太閤山常泉寺】
・所在地:名古屋市中村区中村町木下屋敷47
・宗 派:日蓮宗
・創 建:1606年
・開 基:加藤清正
豊臣秀吉誕生の地とし、豊国大明神の廟堂として創建しました。
ご神体は、木食興山上人が彫刻した豊臣秀吉の束帯唐冠像であり、豊臣秀頼(秀吉の子)に頼み大阪城からこの地に奉ります。
常泉寺の「むすびの輪」、祈願成就の運試しだそうです。
本堂でお祈り後、下の輪をまわし、次に上の輪をまわします。
同じ色のテープがピタリととまれば、願いが叶うと!!!
2つまでのズレはあとひといき!!!
3つ以上のズレは、一層の努力が必要!!!
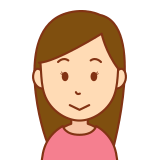
もう1度チャレンジしたい。。

豊臣秀吉像の横には「豊太閤産湯の井戸」があり今でも残されています。
秀吉が生まれた際に、類のない清水が溢れる井戸があったことから「常泉寺」と名付けれたことが縁起書にも記されていたそうです。
1547年に自身で植えた柊もあり、境内には数多くの秀吉ゆかりのものが寺宝として所蔵されています。
妙行寺
【正悦山妙行寺】
・所在地:名古屋市中村区中村町字木下屋敷22
・宗 派:日蓮宗(真言宗から改宗)
・創 建:不明
・本 尊:法華三法
日蓮宗の信者である加藤清正の出生地とされている。
1610年名古屋城築城の際、その余材と普請小屋をもらい受け、妙行寺を自分の生誕地に移築・再建したと言われご先祖ご両親の菩提としたといいます。
加藤清正は築城の名手として言われ、熊本城・名護屋城・江戸城・名古屋城など数多くを手掛けています。
この時期の築城の名手として藤堂高虎がいますが、二人の築城には違いがあります。
加藤清正の築城は、石垣を反らせて高く・虎口を複雑にして、敵への攻撃にそなえる防備を重視した築城に対し
藤堂高虎の築城は、城と城下町との融合、戦のない将来を見込んだ築城です。
もちろん、高虎自身戦国時代の武将ですから石垣も高く積み、堀を設けたりもしています。
が、どんな意図をもって築城していたかの違いがでてる訳です。
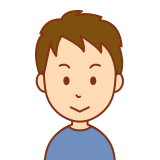
藤堂高虎は、今治城や宇和島城、江戸城などが有名です。
加藤清正は、賤ケ岳七本槍の1人ですので、筋骨隆々の武将イメージです。
しかし、豊臣政権での役割は財務担当だったという話もあります。
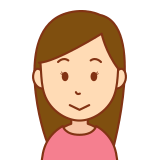
肥後隈本藩主時代の治水工事は有名で
今なお、その威光は熊本県に残っていますからね。
1592年の朝鮮出兵(文禄・慶長の役)時、100~200人を指揮するに過ぎなかった加藤清正は、1万人単位の指揮をとって戦闘した記録があり勝利に導いています。
文武両道の武将だったわけですね。
最後に
豊國参道での太閤まつりに参加したことがある私は、今回非常に楽しんだ時間を過ごしました。
実は常泉寺に行ったことがなかったのです。
加藤清正の妙行寺にも境内入った記憶も。。
愛知県は、三英傑(織田信長・豊臣秀吉・徳川家康)ゆかりの地であるため、関連する武将の登場も多い。
前田利家も名古屋市中村区ではありませんが、隣の中川区が生誕地(荒子)です。
次回はどこに行きましょうかね。
















コメント