真清田神社の創建は神武治世33年、ご祭神は天火明命、邇邇芸命の兄とされる歴史ある神社です。
その中で、本宮荒魂を祀ってある三明神社は別宮にあたり、普段は参拝が出来ない神域に鎮座します。
室町時代には四所別宮とされた、三明神社以外の別宮を参拝しようと思ったのが今回のきっかけです。
みなさんは旧別宮への参拝はすでに行かれましたでしょうか。
第一別宮「三明神社」 別名「印珠宮」「三明印珠宮」
第二別宮「七代宮」 別名「天神社」
第三別宮「両神明社」
「西神明社」 別名「神戸神明」
「東神明社」 別名「濱神明社」
第四別宮「両天王社」
「西天王社」 別名「大神天王」「大神社」
「東天王社」 別名「花祇天王」「御免野天王」「大石社」
別宮
別宮とは「わけみや」の意味で、正宮に次ぐお宮のことです。
参考までに
摂社は、本社のご祭神と関係の深い神様を祀ってある神社
末社は、それ以外の神社です。
摂社の方が、末社よりも格式高いと言われていますが、そこの神社内でのことの話になります。
三明神社
三明神社
ご祭神:本宮荒魂
鎮座地:真清田神社境内
(真清田神社の記事はこちらからどうぞ)
三明神社の参拝は、毎月1日と22日のAM6:00 ~AM9:00からと決めれれています。
本殿の後ろ(北側)に位置しており、本殿脇から入る場所があります。
私が参拝に伺ったときは人もまばらな感じでした。
ただその分、神聖な気分を落ち着いて味わうことができます。
天神社
天神社
御祭神:神世七代
鎮座地:真清田神社境内(服織神社の東側に位置する)
天神社は、現在三末社(愛鷹社、犬飼社、天神社)として祀られています。
ご祭神の神世七代とは、日本書紀の神世七代であり、古事記の神世七代とは一致しません。
そもそも古事記と日本書紀のなかで、神世七代の立ち位置が違います。
古事記は、日本最古の歴史書です。
712年に成立した古事記は、天武天皇の命により稗田阿礼が読み、太安万侶書き記した歴史書です。
簡単に表現すると、天皇家の物語。
日本書紀は、こちらも歴史書です。
720年に完成した日本書紀は、簡単に表現すると日本の出来事をまとめた歴史書。
別の表現で言いますと、「日本はこんな歴史がある国です」と主に海外に向けての書物です。
海外、特に中国(唐の時代)向けですね。
その為、神世七代の立ち位置が変わります。

別天津神や造化三神は、日本書紀に登場しません。
「なぜ登場しないのか?」
古事記の中では
高御産巣日神は、高天原の主役の人
神産巣日神は、出雲の主役の人を古事記内では表しており
天皇家と各豪族との関係性を調和していた、と言われます。
と言っても、天皇家の物語です。やっぱりその中でも主人公が必要!
天之御中主神を最上位に位置することで、まとまりを記していたのでしょう。
当時の時代背景を見ると
古事記完成が712年(元明天皇時)、天武天皇の命により編纂がスタートしています。
天武天皇の治世は、673年~686年です。
538年:仏教伝来
593年:聖徳太子が摂政に就任
645年:大化の改新
672年:壬申の乱
701年:大宝律令
大伴氏、蘇我氏、物部氏、出雲氏、忌部氏、中臣氏など豪族の権力増大する中で、天皇家だけで国を治めることが難しく、豪族の協力なしでは実現できなかった。
701年の大宝律令制定、中央集権国家による日本全国の法体制成立には、各豪族の協力が必要であった。
その中で天皇家中心の物語と言いながらも、各豪族への配慮は必要だったのでしょう。
と創造解釈します。
神明社
神明社
御祭神:天照大御神
鎮座地:一宮市真清田1-1
真清田神社宮前の通りを西へ約100mに神明社がございます。
参道の中央は神様の通り道といいますが、神明社の参道は道幅が狭いので
「参道の中央を歩いていません、端を歩いています」の気持ちで、参拝してきました。
駐車場はございませんので、真清田神社駐車場か近くのコインパーキングにお停めください。
濱神明社
濱神明社
ご祭神:天照大御神
鎮座地:一宮市桜1-16-9
真清田神社より東へ約300mにございます。
東・北面は道路と面していながらも、境内の中は静かな雰囲気がただよう空間です。
神社の右手には船繋松 御古志加計岩(御こしかけ岩)があり
古くこの近辺は、木曽川支流が流れ、舟の往来が盛んであったそうです。
神社が石段上に祀られているのは、その理由もあるからでしょう。
駐車場はございませんので、近くのコインパーキングにお停めください。
大神社
大神社
ご祭神:大物主神、須佐之男神命
鎮座地:一宮市天王3-1
真清田神社から西へ約1Kmの位置に鎮座します。
別名「大神社」「大神天王」、もとは天王社。
天王社は、主に津島神社からの分社が多く、ご祭神は須佐之男命になります。
天照大御神との誓約(うけい)によって生まれた天忍穂耳命(あめのおしほみみのみこと)の子である天火明命、当時は別宮だったとしても関係性は強いですね。
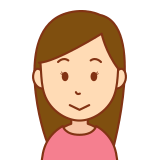
津島神社は
愛知県津島市神明町1に鎮座し
織田家と関係の深い神社です
大神社
尾張国の一宮は真清田神社が一般的ですが、大神神社(おおみやじんじゃ)の公式HPには「相殿・対の宮」と真清田神社とまとめて尾張一宮である。と伝わっている。
確かに、四所別宮は対の宮として記されている神明社はありますが、こと大神社に関してはどうなのでしょうか?
大神神社のご祭神は大物主神、真清田神社のご祭神天火明命との関係性は、薄い。
別宮に相当するのか?摂社に相当するのか?末社に相当するのか?
その線引はどこまでの範囲なのか?
確認する必要がありますね。
ただ、現在は真清田神社の摂社でもなく境外末社とのことから関係性も疑わしいのですが。。。。
大神社だけの神社をみると、大物主神は須佐之男命の子孫にあたるわけですので、これはこれで一宮市花池に鎮座する大神神社(おおみやじんじゃ)の分社に参拝させていただきました。
次回は、本社に参拝に伺います。
の気持ちですね。
大石社
大石社
ご祭神:日本武尊
鎮座地:一宮市桜1-7
真清田神社より東へ約500mの位置に鎮座します。
住宅街の中央に位置し、一見分かりづらい場所です。
駐車場がございませんので、近くのコインパーキングに停めて、歩いて参拝へ伺ってください。
2つの鳥居をくぐり、3対の狛犬を眺め、神社へ参拝までのルートを歩きます。
近づくにつれて、気持ちの高まりを感じる参道になっています。
もとは花祇に鎮座されたが、天正初年に一宮城主関小十郎右衛門が、城の鬼門にあたる鎮守として、現在の地に遷し御石社と改めたといいます。
大石社、旧第四別宮の1つにて西天王社・東天王社と対で第四別宮とのこと。
ご祭神は日本武尊、ここも天火明命との関係性は薄いと思うのですが。
別宮にした経緯が知りたい。
もとは、天王社であることからご祭神は須佐之男命、それがご祭神日本武尊を祀られている。
実際大石社鳥居横の案内板には、第五別宮であったと明記されています。
「真清探桃集」や「真清田神社縁起」によって別宮かどうかの違いもあります。
「古事記」や「日本書紀」の例もあるように、地方豪族に配慮考慮して伝記も作成されているとしたら
真実はあるのか?
最後に
全体的に神社境内は、清潔感がございます。
管理の方や氏子の方たち、日ごろの清掃が行き届いている感じを受けました。
今回強く思ったこと
この先未来の子供たちは、技術科学の進歩により、私たちが知ることが出来なかった真実を知ることが出来るのではないのか?
考古学者や歴史学者の職につく方たちは、将来存在しないのではないのか?
あ~だ、こ~だ、と歴史の楽しみ方が違うのだろうと、勝手に思ってしまいました。
悔しいような、楽しくないような、両方の気分です。
*真清田神社には、山王神社/新八幡宮が旧摂社としてございましたが、それはまた次回にでも。
















コメント